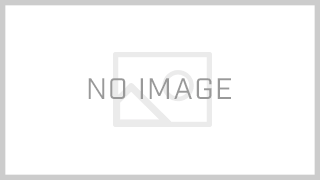地域包括ケアシステム推進に向けた中小病院の看護師の役割
1.はじめに
日本は急速に高齢化が進んでおり、私が勤務する地域の高齢化率は◯%、そのうち独居高齢者は◯%と高率を占めている。このような背景のもと、住み慣れた地域で最期まで暮らせるよう支援する「地域包括ケアシステム」の構築は喫緊の課題である。本レポートでは、私が所属する施設の現状と課題を明確にし、地域包括ケアシステムにおける看護者の役割について考察する。
2.施設の現状と地域の特徴
私が勤務する病院は◯床の急性期一般病院であり、超急性期病院からのポストアキュート(急性期後のリハビリ目的の紹介)患者を多く受け入れており、その紹介率は◯%以上を占める。一方で、施設や在宅からの緊急入院(サブアキュート)患者の割合は◯%未満と少ない。また、再入院率が23%と高く、地域に戻った患者が再度医療機関を利用する状況が課題となっている。
3.課題の分析
地域包括ケアシステムは、「住まい・医療・介護・予防・生活支援」が一体的に提供される仕組みである。当院は超急性期治療後の患者を地域に戻すまでの“つなぎ”の役割を担っているが、以下の課題が浮き彫りとなっている。
-
ポストアキュートに偏った入院経路:施設や在宅からの緊急入院の受け入れが少なく、地域との連携が不十分である。
-
再入院率の高さ:退院支援や在宅移行時の生活支援が不十分であり、継続的なフォローがなされていない。
-
地域の孤立高齢者への支援不足:独居高齢者が多く、退院後の生活を支える体制が整っていない。
これらの課題により、患者が地域での生活を安定して継続できず、再入院に至るケースが多くなっている。
4.看護者の役割
地域包括ケアシステムを推進する上で、看護者の果たすべき役割は極めて重要である。以下に具体的な役割を示す。
-
包括的な退院支援の強化
患者と家族の生活背景や支援体制を把握し、医療・介護・福祉サービスを結びつける退院支援を看護師が中心となって行う必要がある。多職種との協働による退院前カンファレンスの活用や、退院後の生活を見越した支援計画の策定が求められる。 -
地域との連携体制の構築
地域包括支援センターや訪問看護、ケアマネジャーとの連携を強化し、入院前後の情報共有をスムーズに行うことで、切れ目のないケアを実現する。また、サブアキュート患者の受け入れを拡充する体制整備も必要である。 -
健康教育・セルフケア支援の推進
患者や家族に対する健康教育やセルフケア指導を徹底し、再発予防と生活の質の向上を支援する。特に独居高齢者に対しては、服薬管理や生活習慣の指導が再入院予防に直結する。 -
地域資源の把握と活用
看護師自身が地域資源を把握し、必要時に適切な支援につなげられる力を持つことが求められる。生活支援体制整備事業や、地域のボランティアなどとの連携も含めた対応が重要となる。
5.おわりに
地域包括ケアシステムの推進は、患者が自分らしく暮らし続けるために必要不可欠な取り組みである。当院は地域の“つなぎ”としての役割を担っており、看護者はその中核を担う存在である。今後は、地域との連携強化、退院支援の質の向上、再入院防止に向けた看護実践を通じて、地域包括ケアシステムの一翼を担っていくことが求められる。
さあ!頑張って!Report-Go!