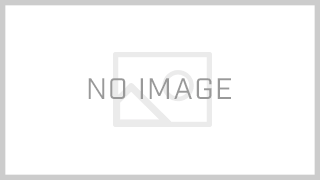認知症高齢患者のケアにおける倫理的問題と看護職の対応
1.はじめに
高齢化の進展とともに、認知症患者の医療・看護の場面における倫理的課題が増加している。認知症患者は、記憶力や判断力が低下し、意思疎通が困難になることが多く、ケアに関わる家族間や医療者間で意見が分かれるケースも少なくない。今回、私は、胃瘻造設と入所を希望する長男夫婦と、自宅での介護を望む次女の意見が対立する事例をもとに、看護職として倫理的にどのように対応すべきかを考察する。
2.事例の概要
認知症高齢患者に対し、長男夫婦は経管栄養のための胃瘻造設と介護施設への入所を希望している。一方、遠方に住む次女は胃瘻に反対し、自分が自宅で介護を行う意思を示している。本人の意思は確認が困難であり、家族間で対応方針が一致していない状況である。
3.倫理的課題の分析
この事例において看護職が直面する倫理的課題は以下の通りである。
-
本人の意思が明確でない中での医療的介入(胃瘻)の可否
-
家族間の意見の相違による意思決定の困難
-
看護職としての中立性の維持と、倫理的支援の在り方
Jonsenらの「倫理的四分割表」に基づいて分析すると、以下の視点が必要である。
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 医学的適応 | 胃瘻造設が患者の予後や生活に与える影響は?侵襲性や合併症のリスクは? |
| 患者の意思 | 過去の発言、表情、生活観などから、可能な限り意志を推定する努力が必要 |
| 生活の質 | 胃瘻後の生活が本人にとって快適で意味のあるものかどうかを検討する |
| 周囲の状況 | 家族の介護力、生活背景、経済的要素、在宅サービスの利用可能性など |
4.看護専門職としての自身の対応
(1) 本人の尊厳と意思を尊重する
たとえ認知症であっても、できる限り本人の価値観や生き方を尊重し、過去の発言や行動から意向を推定する努力が求められる。患者のQOL(生活の質)を重視し、「本人にとって何が最善か」を中心に判断すべきである。
(2) 家族間の対立に中立的に関わる
家族それぞれの立場や思いを傾聴し、感情的対立が激化しないように配慮しながら、話し合いの場(家族会議など)を設定し、合意形成を支援する。
(3) 多職種チームとの連携
医師、ソーシャルワーカー、ケアマネジャーなどと連携し、倫理的視点を共有する。必要に応じて倫理カンファレンスを実施し、チームでの意思決定を図る。
(4) ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の活用
事前に本人や家族と治療やケアの方向性について話し合うACPを導入・推進することにより、本人の意向に沿った医療や介護の選択が可能になる。
(5) 看護職自身の倫理的振り返り
判断に迷う場合は、看護師としての立場を明確にし、上司や同僚と話し合いを重ね、倫理的な支援の在り方を振り返る姿勢が重要である。また、必要に応じて院内の倫理委員会での意見を求めることも必要。
5.まとめ
認知症高齢患者のケアにおいては、本人の意思が不明瞭な場合に家族間で意見が対立することがある。看護職は、患者の尊厳と最善の利益を常に意識しながら、中立的かつ多職種連携の中で倫理的な調整役を果たすことが求められる。倫理的判断に迷う状況こそ、看護職の専門性と人間性が問われる場面であり、今後も倫理的感受性を高め、実践力を養っていく必要がある。
これに、自部署での具体的な例や、実際に行動した内容などを盛り込んでみて!
さあ!report-Go!