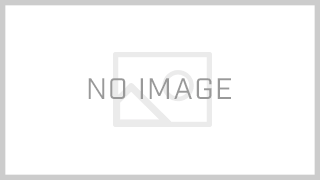そろそろセカンドレベル研修受講の申込時期になりましたが、小論文課題で悩んでいませんか?課題が「あなたの部署・部門を現状分析し、あなた自身の取り組むべき看護管理上の課題について述べてください。」の時、「看護補助者との協働・タスクシフト」のテーマを例にお話しします。
ここでは、部署・部門の現状を分析し、管理者としての課題を述べることが求められます。以下の構成で書くと、論理的で説得力のある小論文になります。
【小論文の構成】
1. 導入(テーマの導入と背景)
- 現在の所属部署・部門の概要を簡潔に説明(例:急性期病棟、回復期病棟、外来など)。
- 看護補助者との協働やタスクシフトの必要性について触れ、現場の課題意識を示す。
2. 本論①(現状分析)
- 看護補助者がどのような役割を担っているかを説明。
- 既に取り組んでいるタスクシフトの状況(進んでいる点・進んでいない点)を述べる。
- 現状の課題を具体的に挙げる(例:業務範囲の曖昧さ、教育不足、コミュニケーションの課題など)。
3. 本論②(看護管理上の課題と解決策)
- 自身が管理者として取り組むべき課題を明確に述べる。
- 課題解決のために行う具体的な対策(例:業務の明確化、教育体制の強化、多職種連携の推進など)。
- 期待される成果を示す(例:看護師の業務負担軽減、ケアの質向上、人材定着率の向上など)。
4. 結論(今後の展望)
- 課題解決後の理想的な姿を描く。
- 自身が看護管理者として目指す役割を述べる。
【例文の構成】
1. 導入(テーマの導入と背景)
私の所属する〇〇病棟では、急性期患者のケアを担っており、近年、患者の重症化や多様化に伴い、看護業務の負担が増加している。その中で、看護補助者との協働を強化し、タスクシフトを推進することが求められている。しかし、現状では役割分担が不明確であり、タスクシフトが十分に機能していない。そこで、看護管理者としてこの課題に取り組む必要があると考えた。
2. 本論①(現状分析)
当病棟では、看護補助者が患者の生活援助(清潔ケア、移乗介助など)を担当している。しかし、以下の課題が挙げられる。
① 業務範囲の不明確さ:看護師と看護補助者の役割が曖昧で、補助者が対応できる業務を看護師が担っている場面が多い。
② 教育体制の不足:看護補助者への教育機会が限られ、業務の質にばらつきがある。
③ コミュニケーション不足:情報共有が不十分であり、ケアの統一性が欠けることがある。
3. 本論②(看護管理上の課題と解決策)
現状分析から看護補助者へのタスクシフトを実践する上での課題は以下の3点である。
- 業務範囲の明確化と標準化
- 看護師と看護補助者の業務範囲を明確にし、タスクシフトの基準を設定する。
- 具体的な業務マニュアルを作成し、実践的なルールを確立。
- 教育体制の強化
- 看護補助者向けの研修プログラムを整備し、安全なケア提供のための知識を向上。
- 定期的なOJTを導入し、看護師と補助者が協働して学べる機会を増やす。
- 情報共有の強化
- 看護師と看護補助者の定期的なカンファレンスを実施し、業務の進捗確認や意見交換の場を設定。
- 電子カルテや申し送りを活用し、情報伝達の効率化を図る。
4. 結論(今後の展望)
これらの改題解決により、タスクシフトの適正化が進み、看護師の業務負担軽減と患者ケアの質向上が期待される。さらに、看護補助者が自身の役割を明確に認識し、やりがいを持って業務に取り組める環境が整う。私は看護管理者として、チーム全体の働きやすさを向上させ、より良い医療提供体制の確立を目指していきたい。
【書き方のポイント】
✅ 現状分析を具体的に書く(業務範囲、教育、コミュニケーションなどの問題点を整理)
✅ 管理者の立場から課題を設定する(現場視点ではなく、組織全体の視点で考える)
✅ 実践的な解決策を示す(業務の標準化、教育強化、情報共有の仕組みなど)
✅ 成果や今後の展望を明確にする(患者ケアの質向上、スタッフの定着率向上など)
この構成で、自身の経験を交えて具体的に書くと、説得力のある小論文になりますよ!
さあ!まずは書いてみて!Report-Go!