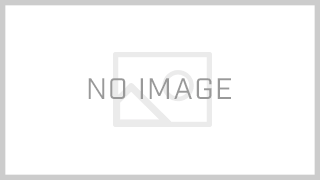地域包括ケアシステムの推進に向けた看護師の役割
~超急性期病院(大規模病院)に勤務する看護師の役割~
1.はじめに
日本の高齢化に伴い、医療と介護を切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築が求められている。特に急性期医療の中心である大規模病院では、高度な医療を提供する一方で、患者の生活再建や地域移行に向けた支援も必要とされる。今回、超急性期病院における現状と課題を整理し、地域包括ケアシステムにおける看護師の役割について考察する。
2.施設の現状と課題
私が勤務する急性期病院は、年間◯件以上の救急搬送を受け入れており、地域の救急医療を担う中核病院である。平均在院日数は◯日と短期であり、急性期治療を速やかに行ったのち、次の療養先への移行が求められている。にもかかわらず、在宅復帰率は◯%未満と低く、患者の多くが回復期病院や介護施設に移行している現状がある。
このような背景には、以下のような課題があると考えられる。
-
急性期治療に集中するあまり、入院早期からの退院支援が不十分
-
地域との連携が弱く、在宅復帰に向けた調整が進みにくい
-
高齢・多疾患患者に対する生活視点でのアセスメントの不足
-
家族や地域資源との情報共有不足
これらは、地域包括ケアシステムの円滑な運用を妨げる要因であり、看護師が介入することで改善可能な領域も多い。
3.看護師の役割
超急性期病院の看護師は、命を守る医療の最前線にいる一方で、患者の「その後の暮らし」まで見据えた視点が必要である。地域包括ケアシステムにおける看護師の役割は以下のとおりである。
-
入院早期からの退院支援の推進
看護師は入院直後から退院後の生活を意識し、生活背景や家族状況のアセスメントを行う。医療ソーシャルワーカー、退院支援看護師と連携し、早期に退院調整を開始する体制づくりが求められる。 -
在宅復帰を見据えた看護計画の立案
在宅療養を想定した看護支援を実践することが重要である。たとえば、服薬管理の練習、排泄や移動などのADL支援、家族指導などを含んだ看護計画が必要である。 -
地域との連携・情報共有の促進
かかりつけ医、訪問看護、ケアマネジャーなど地域の関係者と積極的に情報共有を行い、退院後の生活を支える「橋渡し」としての役割を果たす。退院前カンファレンスの活用や、地域連携パスの推進も効果的である。 -
家族への支援・教育の充実
在宅療養を支える家族の不安や負担感を軽減するため、看護師による教育・心理的支援が不可欠である。疾患や療養生活に関する情報提供、介護技術の指導、医療機器の取り扱い支援などを通じて、家族が安心してケアに臨めるよう支援する。 -
多職種連携の中での調整役
医師・リハビリ職・薬剤師・栄養士など多職種がかかわる中で、患者に最も近い看護師が調整役として全体像を把握し、情報を集約・伝達することが重要である。
4.おわりに
超急性期病院における看護師の役割は、単なる治療の補助者ではなく、患者の生活をつなぐ支援者であるべきである。地域包括ケアシステムを推進するためには、看護師が「生活の場への移行」を見据えた視点を持ち、地域との連携を積極的に担う必要がある。今後は、病院完結型の看護から、地域・在宅を意識した「つながる看護」への転換が求められる。
これに、自院のデータや現状を盛り込むと、さらに具体的なレポートになりますよ。
さあ!手を動かして!Report-Go!