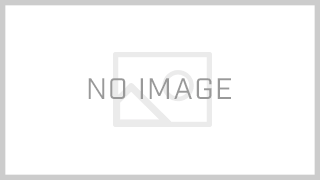倫理的ジレンマにおける訪問看護師の対応
―利用者が日常生活援助を拒否する場面を通して―
1.はじめに
訪問看護の現場では、利用者の生活の場に深く関わるため、援助を受け入れない、あるいは拒否する場面に多く直面する。こうした状況では、看護師が「これでよいのだろうか」と疑問を感じたり、苦悩や不快感を抱くなど、いわゆる倫理的ジレンマが生じやすい。今回、利用者が日常生活行動への援助を拒否する場面を取り上げ、倫理的視点から看護専門職がどのように対応すべきかを考察する。
2.背景と倫理的課題
訪問看護においては、看護師が専門職としての知識や技術をもって援助を行おうとしても、利用者がそれを受け入れないことがある。たとえば、入浴、服薬、清潔援助、食事・水分摂取など、生命や健康に直結する行為であっても、本人の意向が優先されることが多い。その中で看護師は「健康を守るために行いたいこと」と「本人の意思を尊重すべきこと」との間で板挟みになる。これは、「自律尊重」と「善行・無危害」の原則が衝突する典型的な倫理的ジレンマである。
3.事例
80代後半の独居高齢女性。認知機能は軽度低下しているが、意思疎通は可能。清潔保持の援助として入浴や清拭を提案したが、「面倒くさい」「人に身体を見られるのが嫌だ」と強く拒否。看護師としては、皮膚の状態や感染リスクが気になるものの、無理に行うことへの抵抗もあり、ジレンマを感じた。
4.対応と工夫
この場面においては、以下のような対応を行った。
-
利用者の意向の傾聴と背景理解
→入浴への拒否には、過去の羞恥心や他者との関係性への不安があることが分かった。 -
リスクの丁寧な説明と選択肢の提示
→「入浴しないことで皮膚のかゆみが強くなる可能性がある」と説明し、「全身でなくても顔だけでも拭きましょうか?」と提案。 -
小さな一歩の提案
→最初は手浴のみから始め、徐々に身体の一部へと拡大。利用者のペースに合わせることで信頼関係が構築された。 -
チームカンファレンスの実施
→ケアマネジャーや訪問介護員と連携し、本人にとって「負担感のない援助方法」を検討した。 -
記録と振り返りの共有
→看護師間で記録を共有し、次回訪問時の対応に活かした。
5.考察
本事例を通じて、訪問看護師が倫理的ジレンマに直面した際には、「正しいことを押し付ける」のではなく、「本人の意思を尊重しながらリスクを最小限に抑える」視点が重要であることが分かった。医療倫理の4原則(自律尊重・無危害・善行・正義)を軸に考えることで、冷静に対応できる。また、看護師一人で抱え込まず、チームでの情報共有やカンファレンス、スーパービジョンを活用することで、倫理的な重圧を軽減し、より良い支援につなげることができる。
6.おわりに
訪問看護は、病院とは異なり、利用者の「暮らし」に寄り添う支援が求められる。そのため、倫理的ジレンマに直面することも多いが、それは看護師として誠実に向き合っている証でもある。今後も倫理的視点を持ち、利用者の尊厳と健康のバランスを大切にしながら支援を続けていきたい。
参考にしてみてね。
さあ!repot-Go!