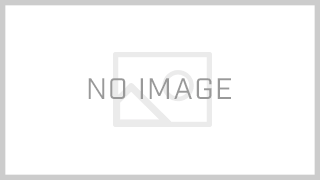セル看護方式(Cell Nursing System)は、看護師が小規模なチーム(セル)を作り、 患者のケアを包括的に担当する看護提供方式です。患者に対する責任の明確化や看護の 質向上を目的としています。
1. セル看護方式の特徴
① 少人数のチーム(セル)で患者を担当
- 3~5人程度の看護師で1つのセルを形成
- 特定の患者群を継続的に受け持つため、患者との関係が深まり、個別的なケアがしやすい
② 患者中心のケアを実現
- 看護師がリーダーシップを持ち、医師・看護補助者・多職種と連携
- 患者の状態に応じた柔軟な対応が可能
③ 看護師の責任が明確
- 各セルにリーダー(セルリーダー)を配置
- セルごとにケアの計画・実施・評価を行い、責任を持って看護を提供
④ チームの柔軟性が高い
- 看護師の経験やスキルに応じて役割を調整
- OJTを通じた教育やスキル向上がしやすい
2. セル看護方式のメリット
① 患者満足度の向上
- 担当する看護師が固定されやすく、継続した看護が可能
- 患者にとって「いつも同じ看護師が関わる」ことで安心感が生まれる
② 看護の質の向上
- 患者の情報共有がスムーズになり、個別性の高いケアを提供できる
- 責任を持った看護が実現し、専門性の向上にもつながる
③ 看護師のやりがいが向上
- 自分のケアが患者にどう影響を与えたかを実感しやすい
- チームワークが強化され、職員のモチベーションが向上
④ 柔軟な勤務体制が可能
- セル内で業務を調整できるため、急な勤務変更などにも対応しやすい
- 仕事の負担をセル内で分担できる
3. セル看護方式のデメリット・課題
① 人員配置の課題
- 少人数でセルを組むため、人員が不足すると機能しにくい
- 夜勤や休日の看護体制の調整が難しいことも
② 看護師間のスキル差
- 経験が浅い看護師が多いセルでは、業務負担が偏る可能性がある
- OJTや研修による教育が不可欠
③ 多職種との連携が必要
- 医師やリハビリ職と情報共有をしっかり行わないと、ケアの統一性が崩れる
- 情報共有ツール(カンファレンス、電子カルテなど)の活用が重要
④ 役割分担の明確化
- 「誰が何をするか」を明確にしないと、業務が偏ることも
- タスクシフト・タスクシェアを組み合わせて、セル内の業務効率を高める必要がある
4. セル看護方式の導入ステップ
① 目的とゴールの明確化
- なぜセル看護方式を導入するのかを整理し、組織内で共有する
- 看護部内での合意形成を図る
② 業務分析
- 現在の業務の流れを分析し、セル看護に適した業務分担を検討
- 看護補助者や多職種との役割分担も考慮
③ 試験導入
- 一部の病棟やユニットで試験的に運用
- 効果測定を行い、課題を明確にする
④ フィードバック・改善
- 看護師の意見を集め、柔軟に改善
- 教育体制や情報共有の強化を進める
⑤ 全面導入
- 試験導入の結果を踏まえ、全病棟へ展開
- 継続的な評価と改善を行い、定着を図る
5. セル看護方式と他の看護提供方式との違い
| 看護提供方式 | 特徴 | メリット | 課題 |
|---|---|---|---|
| チームナーシング | 看護師がチームを組み、役割を分担してケアを提供 | 責任の分担が明確、業務効率が良い | 個別性の高いケアが難しい |
| プライマリーナーシング | 1人の看護師が特定の患者を継続して担当 | 継続性が高く、責任感が強くなる | 1人に負担が集中しやすい |
| セル看護方式 | 少人数のセルで特定の患者群を担当 | 柔軟なチーム運営が可能、看護の質向上 | 人員配置や役割分担が課題 |
6. セル看護方式を成功させるポイント
✅ 情報共有の仕組みを整備する(カンファレンス・電子カルテ活用)
✅ 看護師のスキルアップを支援する(OJT・教育制度の強化)
✅ タスクシフト・タスクシェアを活用する(看護補助者との協働)
✅ 組織文化として定着させる(リーダーシップの発揮、定期的な評価・改善)
7. まとめ
セル看護方式は、「チームワークを活かした継続的な看護提供」を目的とした看護提供方式です。看護の質向上や患者満足度の向上に貢献できますが、適切な業務分担や人員配置が重要になります。
導入を検討する際は…
✅ 現在の看護体制の課題を分析
✅ 試験的に導入し、実際の運用を確認
✅ 看護師や多職種との協働を意識しながら進める
これらを意識すると、スムーズな導入・定着が可能になります。