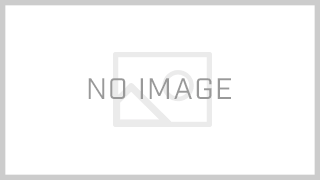レヴィンの変革モデルで進める「看護業務のタスクシフト」
ファースト・セカンドレベル研修始まりましたね。そろそろ、最初のレポート課題が出される頃ですね。レポートってどうやって書けばいいの?と思っているそこのあなたへ朗報です。このレポートGOでは、看護レポートお助けサイトです。今回は、レヴィンの変革理論を使った看護補助者へのタスクシフトについて考えます。参考にしてね。
🧊【ステップ1】解凍(Unfreezing)
―「現状を見直し、変革の必要性を共有する」段階
■ 主な取り組み:
-
タスクシフトが必要な理由を共有
例:「業務量が多く、看護師が患者のそばに行けない」「転倒リスクに即応できない」など -
看護業務の現状分析(タイムスタディ、業務日誌、インシデント分析)
-
看護補助者の活用状況の見える化
-
感情面への配慮(「業務を丸投げされた」などの不安の傾聴)
■ 成果目標:
-
看護師・補助者が「今のままではいけない」と感じる状態をつくる
🔄【ステップ2】変革(Changing)
―「実際に新しい行動・仕組みに移行する」段階
■ 主な取り組み:
-
タスクシフトの対象業務を明確化(例:環境整備、清拭、移乗など)
-
手順書や業務分担表の整備
-
看護補助者への研修とスキルチェック
-
トライアル導入(特定日・特定時間のみなど)
-
看護師と補助者の連携ルール確立(記録、申し送り、報告など)
■ 成果目標:
-
試行で「やってみたら意外とできた」という小さな成功体験をつくる
-
実施後に必ずフィードバックを実施(不安・課題の吸い上げ)
❄【ステップ3】再凍結(Refreezing)
―「新しい状態を定着・安定させる」段階
■ 主な取り組み:
-
タスクシフトの業務を標準化(マニュアル・業務分担表を見直し)
-
成功事例の共有、他部署への水平展開
-
定期的な見直しと教育体制の継続
-
感謝の言葉や成果の可視化(ありがとうカード・インジケーター評価など)
■ 成果目標:
-
補助者の役割が組織に定着し、看護師も安心して任せられる状態をつくる
-
チームとしての信頼関係が深まる
🔑 補足:変革を成功させる3つの鍵
-
現場の“痛み”を丁寧に共有(数字と声を両方使って)
-
小さな成功とフィードバックのループを大切に
-
役割が違っても「同じ患者を支えている」意識づくり
さあ!report-Go!