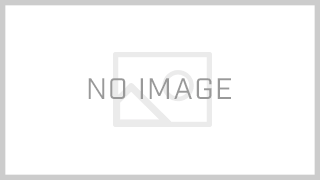ストレスチェックは、それを「チェックするだけ」で終わらせず、職場環境の改善につなげることが重要です。以下のように活用することで、効果的なメンタルヘルス対策ができます。
① 結果を分析し、職場単位での課題を明確にする
ストレスチェックの集団分析結果を活用し、部署ごとのストレス要因を明確にしましょう。
分析のポイント
-
高ストレス者の割合が多い部署があるか?
-
どの要因(業務負担・対人関係・ワークライフバランスなど)が影響しているか?
-
過去のデータと比較し、改善傾向や悪化傾向があるか?
活用例
✅ 「人間関係のストレスが高い」と判明 → 定期的な1on1面談を実施
✅ 「仕事の負担が大きい」と判明 → タスクシフトの推進、業務改善を検討
② 高ストレス者へのフォローアップ
ストレスチェックで「高ストレス」と判定された職員には、産業医面談や管理者によるフォローを実施することが大切です。
ポイント
-
産業医面談を案内し、必要に応じてカウンセリングを受けられるようにする
-
本人の希望があれば勤務調整(夜勤回数の軽減など)を検討
-
看護管理者が「最近どう?」と声をかけやすい環境を作る
活用例
✅ 夜勤回数が多い高ストレス者には、希望を聞いてシフト調整
✅ メンタル負担が大きいスタッフには、業務内容を一時的に見直す
③ 組織全体のメンタルヘルス施策を強化
ストレスチェックの結果を踏まえて、組織としての対応を考えることも重要です。
職場のメンタルヘルス対策の例
-
上司・部下のコミュニケーション強化
-
1on1面談の実施
-
「ありがとうカード」や感謝を伝える仕組み作り
-
-
休息を取りやすい環境作り
-
看護師が仮眠をしっかり取れるようにする
-
リフレッシュスペースの整備
-
-
業務負担を減らす
-
タスクシフト・業務整理を進める
-
残業削減のための仕組み作り(業務の見直し・ICT活用など)
-
活用例
✅ 高ストレス者が多い部署 → 話しやすい環境を作るために「1on1面談」を導入
✅ 全体的にストレスが高い → 「業務負担の見直し」を実施し、タスクシフトを進める
④ 結果をフィードバックし、継続的に改善
ストレスチェックの結果は、看護部や各部署の管理者と共有し、改善策を継続的に進めることが大切です。
-
定期的な振り返り
-
半年後や1年後に再評価し、改善効果を測定
-
-
スタッフへの情報共有
-
「ストレスチェックの結果をもとに、このような対策を行います」と周知
-
-
管理者が率先して変えていく
-
看護師長として「働きやすい職場を作る」という姿勢を見せる
-
まとめ
ストレスチェックは「やって終わり」ではなく、
✅ 職場環境の課題を明確にする
✅ 高ストレス者をフォローする
✅ 組織の改善策につなげる
✅ 結果をフィードバックし、継続的に取り組む
ことが大切です。
「看護師が健康で長く働ける職場」を作るために、ストレスチェックの結果を活用していきましょう!