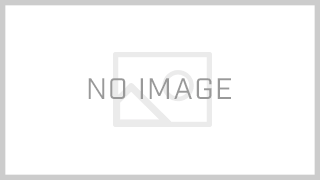Ⅰ.はじめに
看護の現場では、医療安全の確保は最重要課題である。従来は「エラーをいかに減らすか」という視点(Safety-I)が中心であったが、複雑な医療現場ではすべてのリスクを事前に排除することは困難である。しかし、レジリエンス・エンジニアリングの「予見する・モニターする・対応する・学習する」という4つの能力を組織として高めることで、安全性と効率性を両立させることが可能である。今回、誤配膳事例をもとに、部署全体がレジリエンスを発揮できるための安全管理について考察する。
Ⅱ.事例概要
全身麻酔手術当日、患者に「誤って朝食が配られても食べないでください」と事前に説明していた。実際に誤って朝食が配膳されたが、患者は摂取せず、インシデントを回避できた。これは看護師のリスク予見と患者教育による適応的な対応であり、レジリエンスの発揮と解釈できる。
Ⅲ.考察
-
予見する能力(Anticipate)
誤配膳の可能性を想定し、事前に患者へ説明を行った点はリスクの先読みであった。今後は手術や検査時の誤配膳リスクをリスト化し、チームで共有する体制が必要である。 -
モニターする能力(Monitor)
実際の配膳を常時スタッフが監視することは困難であるため、患者を「モニター役」として位置付けた。この工夫は患者参加型の安全確保の好例であり、今後は患者や家族を含めた多層的モニタリング体制を標準化することが望まれる。 -
対応する能力(Respond)
実際に誤配膳が生じたが、患者が食べなかったことで安全を確保できた。組織としては、想定外の事態に柔軟に対応できるよう、シミュレーション教育や権限移譲を進め、現場判断で対応できる力を育成することが重要である。 -
学習する能力(Learn)
今回の事例は「失敗を免れた」ではなく「成功体験」として評価すべきである。インシデント報告は失敗事例だけでなく成功事例も対象とし、良い実践を組織全体で共有・標準化することで、安全文化を育成できる。
個人の工夫を「組織知」として共有し、全員が使える仕組みに落とし込むことが重要となる。そのためには、今までのインシデントレポートだけではなく、Safety-IIレポートの収集やそれを共有するための発表の場を設けたり、「インシデント回避褒めカード」等の活用が有効である。さらに、心理的安全性の確保、多職種連携、情報の見える化を組み合わせることで、部署全体が「安全を守る力」を日常的に発揮できる組織文化を醸成できると考える。
Ⅳ.結論
今回の事例から、レジリエンスを発揮することで事故を未然に防ぐことが可能であることが示された。部署全員が安全かつ効率的な看護提供能力を高めるためには、レジリエンス・エンジニアリングの4能力を組織的に育成・活用する安全管理が不可欠である。このように失敗を減らすSafety-Iと、成功例を増やすSafety-IIを両立させることで、持続可能な安全文化を構築できる。
レポート課題のお手伝いできましたか?あなたにもインシデントを回避できたエピソードが1つや2つあるはずですよ。思い出して、レポートにしてみましょう。
さあ!Report-Go!